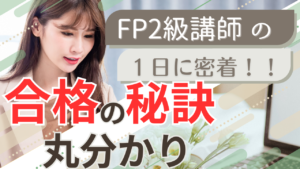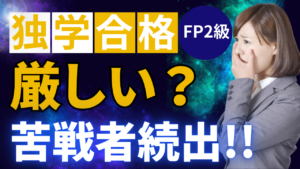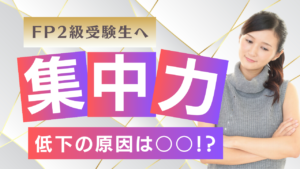こんにちは。
今回はこれまでに100名以上の受講生と話して見えてきた不合格になる人の共通点をお伝えさせていただきます。
もし不合格になりたくなければ、不合格を経験した人と同じことをしなければ良いのです。
プロ野球の野村克也元監督の名言をご存知でしょうか?
「勝ちに不思議の勝ちあり、
負けに不思議の負けなし」
負けるときにはそれにつながる必然的な要因があるという教えですね。
つまり、不合格になるということは必ず何かしらの要因があって、不合格になっているわけですから、その要因を突き止める必要があります。
仕事でもそうじゃないですか?
もし仕事でミスをしたときって、その後に原因を考えて今後同じミスをしないように対策を打って、行動を変えますよね。
なぜ仕事だとそれを意識するのに、資格の勉強になった途端、敗因分析と適切な対策を打たない人が多いのでしょうか。
1度や2度ならまだしも、3度、4度、5度・・・と2年以上かけて受験し続けている人もざらにいらっしゃいます。
FP2級はさっさと合格して、別の勉強に充てた方が人生早くステップアップできると思いませんか?
何度も何度も受験する時間が、もったいないなぁって思うわけです。
というわけで、早速本題に移っていきます。
勉強法がブレブレ
不合格になった方に、これまでどういった勉強法をされてきたんですか?とお伺いすると、
- テキスト読む
- 動画解説みる
- ノートにまとめる
- 問題集を解く
- 過去問解く
こんな回答が返ってきます。
そこまでは特に問題ないんですよ。
問題はこの次です。
それぞれの勉強の時期やタイミング、使い方は合格に繋がる方法だと確信をもって進めることができていましたか?と。
ほぼ全員が「いいえ」という回答でした。
酷い人だと、その日のその瞬間の気分で、動画みたり、テキスト読んだりしているんです。
勉強する分野も「今日はなんとなくライフプランニング!」みたいな、その場のノリで決めて、やってるんですね。
正直申し上げてこれでは合格は程遠いと思います。
限りある時間で勉強して、合格という成果に繋げるためには、必ず目的を明確にして、ツールを使いこなさなければなりません。
その日の気分や、なんとなくという理由で勉強していては、いつまで経っても合格できないのも無理はありません。
必ず、ゴールを見据えて、そこに繋がる勉強法をするから合格が見えてくるんです。
ブレブレの勉強法で合格できるほど、FP2級は甘くないんです。
モチベーションに左右される
なぜ不合格になったと思いますか?と質問すると一定数の人からは、
「途中で勉強のやる気がでなくなって勉強ストップしてました」という
回答が返ってきます。
つまり、そもそも勉強時間の確保すらできていなかったという話です。
特に、これは金融機関にお勤めの方が多い印象です。
推測するに、会社の昇進条件になっていて半強制的に受けなければならないから受験するといった状況なので本当の意味で自分で勉強したい!となっていないんですよね。
人からやらされることに対して、やる気が起きないのはやむを得ないのかなとは思います。
ただ、そうは言っても自分の人生に関わることではあるので、資格試験に落ち続けて時間を無駄にして良いのか?社内の人から勉強ができない人というレッテルを貼られても良いのか?昇進を遅らせても良いのか?と、自問自答する必要はあると思います。
そんな方には、自分の人生に一度本気で向き合ってみたらどうですか?と私は伝えたいです。
実際、過去に、FP2級に3回も落ちた私の部下に指導する際、最終的にどんな人生を送りたいのか?と人生を考えてもらったことで、勉強に対しての本気度が上がったことがあります。
そもそも論、モチベで勉強が左右されたダメだよって言いたいですね。
仕事の日、朝起きてその日の気分で出勤するか休むか考えますか?
ほとんどの方が、やる気がおきなくても、出勤しますよね?
勉強も一緒です。
やる気が出る出ないにかかわらず、合格すると決めたなら、ただ「やる」だけなんです。
ただ「やる」だけなんですが、そこの壁が乗り越えられない受験生が結構いらっしゃるんですよね。
インプットばかりに時間をかける
書店で購入したテキストや解説動画、今は便利な世の中になったこともあり、情報を入手できるツールはたくさんあります。
ひたすら動画見てるとか、テキスト読むとか、インプットの時間が多い人はだいたい不合格になっています。
ツールが上手く使いこなせていない典型例です。
インプットの時間が多すぎることで引き起こされる現象は主に2つあります。
1つ目は、いざ問題を解いても解けないといった現象です。
インプットできたら問題がスラスラ解けると思いがちです。
実際何名もの受験生と話してきて、インプットしたことを問題解いてスラスラ解けましたか?と聞くと、だいたいが「No」という返事が返ってきます。
これはなぜだと思いますか?
インプットで認識した知識と、いざ問題を解いたときに問われていることが一致していないからです。
だからインプットできたと思っても、いざ問題を解くと「あれ?」という感覚になるのです。
2つ目は、本番で思い出せないという現象です。
記憶というものは、「覚える➡忘れる➡思い出す」
このステップを踏むことが重要になってきます。
インプットが多いということは、「覚える」の1点集中になっているんです。
覚えたことを忘れていることすら気付かないケースもありますし、本番までに「思い出す」という経験も少なすぎるので、試験当日、「あれ、なんだっけ・・・」となるのです。
勉強計画を立てるときには、必ずインプットとアウトプットの割合を意識して計画を立ててみてください。
丸暗記で乗り切ろうとする
FP2級の範囲は膨大です。
しかも最近の試験はかなり深いところまで突っ込まれるようになっています。
つまり、表面上の浅い知識を丸暗記しているだけでは、到底太刀打ちできなくなってきているのです。
テキストの中身を見ても、暗号に見えていませんか?
そんな暗号を丸暗記したとて、実際の試験で問われ方が少し変わるだけで、もう対応できなくなります。
しかも、丸暗記には限界があります。
6分野で覚えることも多いので、丸暗記しても最初に勉強したことが最後の方には記憶から抜け落ちていることでしょう。
結局、試験直前になって、数か月前に解けていた問題が解けなくなったと焦ることになります。
なので、丸暗記は極力減らし、「理解」に重きを置いてください。
一度時間をかけてでも、理解し「なるほど!分かった!」という感覚を持つことができれば、ただの丸暗記に比べて記憶にも残りやすくなります。
FP2級に合格し、合格後も知識を活かしていきたいと考えているのであれば、「暗記力」ではなく「記憶力」を鍛えて、使える知識を増やしていきましょう。
丸暗記から脱却すれば、勉強の苦痛から解放されます。
問題を解いていても、選択肢に対して一人でツッコミができるようになるので、勉強が楽しくなります。
できなかったことが、できるようになったら嬉しいですよね。
ぜひ、その感覚を味わっていただきたいなと思います。
過去問の正答率が6~7割で安心している
私のこれまでの統計データ上、試験直前の過去問の正答率から比べると、試験本番はだいたい10%~20%落ちます。
例えば試験直前の過去問の正答率が60%だった人は、試験当日の正答率が50%前後になるといった具合です。
だから、過去問の正答率が6~7割ということは、試験本番が5~6割になる可能性が高いので、合格できる可能性は極めて低いと考えています。
完全に運ゲーとなるのです。
試験当日ある程度余裕をもって合格したいなら、過去問は正答率9割を目指してくださいねと受講生の皆さんにはお伝えしています。
実際の受講生の中には、過去問が9割超えていて当日も9割超えていた方もいらっしゃいましたが、だいたいは正答率8割前後に着地しています。
苦手な問題が続いたり、その日たまたま調子が悪かったとしても正答率6割は固いかなという感じです。
これから勉強をする方は、ぜひ、過去問の正答率を意識してみてください。
まとめ
今回は不合格を経験してきた方へのインタビューから見えてきた共通点をお伝えさせていただきました。
一度、不合格を経験されたことがある方は、当てはまるものがあったのではないでしょうか?
次こそ合格したい!と思うのであれば、不合格者と同じ思考回路にならないように、意識的にご自身の行動を変えて行くことが必要です。
ぜひ、今の行動が合格に繋がるものになっているのか?という観点から、振り返ってみてください。
応援しております。
最後までご覧いただきありがとうございました!