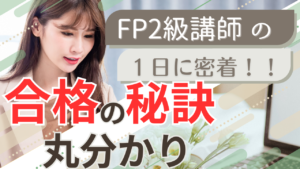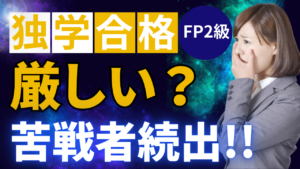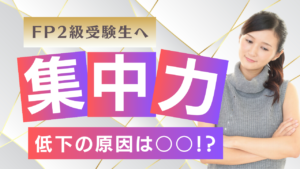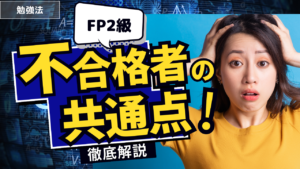今回は、FP2級の勉強を暗記で乗り切るのか?理解して解けるようになるのか?ということについてお話していきます。
受験生に悩みを聞いてみると、
・テキストに書いていることが暗号のように見える
・公式が覚えられない
・過去問の答えを覚えてしまった
こんな言葉が返ってくることがよくあります。
あなたはどうですか?
暗記には限界がある
FP2級は6分野から成り立っており、範囲は広いです。
FP3級と比べても内容が深く複雑になるので、テキストに書いていることを覚えようと思っても、途方もなく感じることだと思います。
覚えたと思ったのに、次解いたら忘れていた・・・
なんていう経験があるのではないでしょうか?
年とともに記憶力も悪くなって・・・と嘆く方もいらっしゃいます。
丸暗記で乗り切ろうとすると、いずれ挫折しかけるのがFP2級です。
だから丸暗記で勉強することを個人的にはオススメしていません。
覚えられないという人の共通点
「なかなか覚えられません」という人に、内容をどこまで理解しているか?と聞いてみると、ほぼ答えられない人が多いです。
説明できないということは、テキストに書いていることを自分の中で咀嚼して腑に落とすことができていないということなんです。
内容を理解しておらず、ただ言葉や公式を暗記しようとしているので、なかなか覚えられず勉強に苦戦しています。
ちなみに、私は昔から記憶力が悪いことがコンプレックスでした。
中学の国語の時間を今でも忘れません。
古文で竹取物語を暗記する時間がありました。
「今は昔、竹取の翁といふ者ありけり。」と暗記できた人から、先生のところに行って発表して、全部言えたら合格という授業だったんですね。
私は必死に暗唱して覚えようとしたのですが、なかなか覚えられなくて焦っていました。
周りのクラスメイトは次々と合格していくんです。
やばい、あと5人、4人、3人・・・と焦れば焦るほど覚えられませんでした。
そして結局、私はクラスで一番最後まで残ってしまいました。
凄く悔しかったし、恥ずかしかったです。
その時に改めて、私は覚えることが苦手なんだと痛感しました。
暗記が苦手だからこそ辿り着いた境地
「暗記」が苦手だった私は、とにかく覚えなくても解ける方法を常に考えるようになりました。
少しでも暗記を減らして、勉強ができるようになりたいと思ったんです。
それが今のFP2級勉強法にも繋がっています。
逆に、テキストに書いていることを丸暗記しようとしている人に対して、尊敬の念すら抱きます。
私には絶対無理なことですから・・・
「暗記」を減らして、問題を解けるようになるためには何が必要だと思いますか?
それは「理解」することです。
内容を「理解」しておけば、無理な「暗記」をしなくても答えが導き出せるようになるんです。
例えば、計算式でイメージしてみましょう。
5×(2+3)=?という式があったとします。
答えは25ですよね。
これはカッコを先に計算するというルールを理解しているから、数字が変わっても答えが分かるんですよね。
テキストを丸暗記しようとしている人は、私から見れば、5×(2+3)=25 この計算式と25という答えを必死に覚えようとしているように思えるんです。
そのため数字が変わった途端、答えられなくなります。
これがFP2級の勉強でも同じ事象が発生していると考えています。
四則演算のルールがあり、カッコを先に計算するということを知っておけば、中身の数字が変わっても解けるはずです。
でもそのルールを理解することなく、テキストに書いてある数字をただ覚えようとしている。
これでは試験本番、太刀打ちできないでしょう。
言い方が少し変わったり、応用となると、途端に初見の問題に見えてしまうんです。
無意識のうちに、こういった勉強をしている人が多いんじゃないかなと感じています。
理解のコツ「抽象化」
では「理解」には、どうすれば良いのか?
抽象化して考えるのがポイントです。
先ほどの計算式の例の場合だと、5×(2+3)=? 「2と3を先に足して、5をかける」と覚えるのではなく、「基本は掛け算、割り算が最初だが、カッコがある場合はカッコの中を先に計算する」と認識するということですね。
「自分のなかで咀嚼して、抽象化する」ことが理解には重要です。
「つまり、こういうことだよね」と、自分の頭の中で考えるのです。
中身は一つ一つ違って見えていても、抽象化すると共通点が見えてきます。
そして具体化して内容を落とし込んでいく。
この作業を繰り替えすだけで、丸暗記という力技を使わなくても、無理なく記憶に残りやすくなります。
理解のコツ「人に説明する」
自分が本当に理解できたのか?と確認する方法として、人に説明してみるということが挙げられます。
知識のない人に分かりやすく説明できたら、自分の中でも腑に落として理解ができている証拠です。
逆に、上手く説明できていなければ、理解しきれていないということです。
再度インプットをし直し、どこまで理解できていて、どこから理解できていないのか?を把握する必要があります。
特に私が普段から言っているのは、目の前に小学生ぐらいのお子さんがいて、子供でも分かるように、専門用語を使わずに、説明できるようになりましょうということです。
FP2級の問題文は専門用語のオンパレードです。
いかに専門用語をなくし、分かりやすい言葉に置き換えるか?をミッションにして勉強するだけで、全然理解度が変わってきます。
保険業界の人だとよく分かると思いますが、知識のないお客様に「解約返戻金が~」と言っても伝わらないですよね。
「解約したときに戻ってくるお金」と言い換えないときっと理解してもらえないと思います。
それと同じように、たくさん出てくる専門用語と難しい言葉の数々を、いかに分かりやすい簡単な言葉に置き換えて、腑に落とすかが勉強するときのコツです。
私の受講生には、アウトプットする場を設けたいと思い、複数の受講生が集まってグループ勉強会を実施しています。
アウトプットを希望する受講生が、他の受講生に対して勉強した内容を発表していただいています。
「自分の中で理解して人に説明したものは、実際に忘れにくい」と受講生が仰っていました。
確かに、私も受講生と1対1で個別解説するときに、私が解説をするのですが、一度説明したことは記憶によく残っております。
なんだかんだ私が一番勉強になっているのではないか?と思うぐらい、人に説明をすると覚えますね。
皆さんも、一度テキストから離れて、人に説明をするアウトプットをやってみてください。
理解のコツ「分かりやすいイメージに置き換える」
FP2級の分野は、人によっては生活に馴染みのない分野や項目がありますよね。
まだ人生上で経験したことないことは、イメージができないので、苦手意識を持ちやすいです。
普段、聞かない言葉が出てくると、意味は疎か、読み方すら分からないといったものも出てくると思います。
例えば、相続の分野に出てくる「貸家建付地」(かしやたてつけち)。
この言葉を初めて見る人は、なんて読むのだろう・・・と思った人もいると思います。
これをただこの言葉のまま「貸家建付地」と覚えても良いのですが、それより「人に貸すアパート」と覚えた方がイメージつきませんか?
こんな感じで、たくさん出てくる専門用語や初めて見る言葉はできる限り、自分が知っているものに置き換えて、紐づけながら意味を理解していくんです。
そうすると、学科試験の長い長い文章も、実は分かりやすい簡単な文章に直すことができるんですね。
私の脳内はどうなっているかというと、選択肢を読む➡分かりやすい文章に変える➡どこが間違っているか疑う➡間違っているところを見つけて「そんなわけないでしょ」と突っ込む
こんなステップで正誤を判断しています。
「理解」できたらどうなるか?
ここまで「理解」するコツをみてきました。
本当の意味で「理解」できたとき、自分の中でどんな変化が起こると思いますか?
理解する前は、選択肢を見てもモザイクがかかったような感じです。
分かるような、分からないような・・・
でも一度理解したあとに、再度同じ選択肢を見ると、不思議なぐらいクリアに見えるんです。
視界良好!!となるんです。
これまで難しく感じていた問題が、嘘のように簡単に思えます。
あなたにもこの感覚を味わってほしいなと思います。
この感覚が掴めるようになったら、問題を解くのが楽しくなります。
達成感も味わうことができます。
勉強のスピードが加速します。
騙されたと思って「理解」に重きをおいた勉強を意識してみてください。
急がば回れで、正答率が上がるはずです。
応援しています。