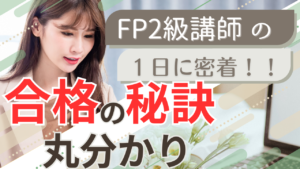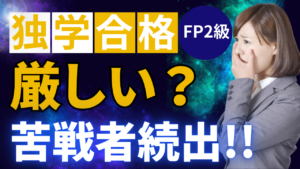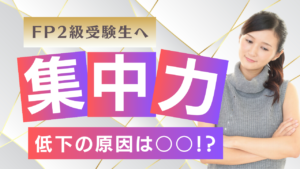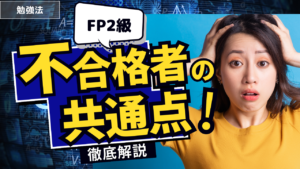FP2級の範囲は幅広く、近年深い知識まで
問われることがあります。
テキストに書いている言葉や数字を
丸暗記するだけでは、
太刀打ちできなくなっています。
丸暗記ではなく、「理解」に重きを置いて
勉強することの重要性は前回の記事で
お伝えした通りです。
では、「理解」するために
どうやって勉強していけば良いか?
ということについて
今日はお話していきます。
理解度の確認は「アウトプット」
理解ができているかどうかを確認するには、
アウトプットつまり問題を解くことが
一番の近道です。
では、問題を解くステップを
イメージしてみましょう。
ほとんどの方が、このような流れで問題集や
過去問題を解くのではないでしょうか?
解説を読んで「なるほど!そういうことか!」と
腑に落ちたらOKです。
でも解説を読んでも「どういうこと?」となる
問題ありませんか?
問題の意味も分からないし、
解説の意味も分からない。
何が分からないかも、分からない。
こんな状況に陥る受験生も少なくありません。
そんなときにオススメの勉強法が
「巻き戻し」勉強法です。
巻き戻し勉強法って何?
初めて聞きましたよね。
私が勝手に名付けた勉強法です。
どういうことかというと、
解説を読んでも意味が分からなかったときに
この勉強法は発動します。
イメージしやすいように、例題を用意しました。
では、タックスプランニングから
法人税の問題です。
ー問題ー
法人が減価償却資産として損金経理した
金額のうち、償却限度額に達するまでの
金額は、その全額を損金の額に算入することができる。
(2023年9月 問37)
○か×か分かりますか?
正解は・・・
○です!
過去問道場さんでの解説は
このように記載されています。
ー解説ー
適切。企業会計上は、費用収益対応の原則に従って法人ごとにどのような方法で減価償却を行っても自由ですが、税法上の損金や経費にできるのは、法人が減価償却費として計上した額のうち法定の償却限度額までの金額に限られます。償却限度額を超える部分の金額は損金不算入となります。
はい、こちらの解説を読んで、
なるほど!OK!と簡単に
理解できた人は基礎知識が
固まっていることだと思います。
でも多くの人は、
解説の内容すら「???」と
なっているのではないでしょうか?
過去問道場さんの解説が
悪いわけではありません。
内容も正しいですし、
なんの問題もないんです。
ただ、受験生は理解に苦しむところなのです。
それは、なぜか??
それは、そもそもの
前提の知識が抜けているからです。
具体例で学ぶ
では、ここから巻き戻し勉強法を実践してみます。
黄色のマーカー部分の言葉の意味を
説明できますか?
適切。企業会計上は、費用収益対応の原則に従って法人ごとにどのような方法で減価償却を行っても自由ですが、税法上の損金や経費にできるのは、法人が減価償却費として計上した額のうち法定の償却限度額までの金額に限られます。償却限度額を超える部分の金額は損金不算入となります。
1つだけ例を出します。
企業会計上と税法上とは何が違うか
ご存知でしょうか?
「会計上」と「税法上」は目的が異なります。
簡単に言うと、
「会計上」は取引先や投資家向け。
会社の経営成績や財政状況をまとめた
「決算書」「財務諸表」の作成を
目的としています。
「税法上」は税務署向け。
会社が納めるべき税金を算出した
「法人税の申告書」を作成することを
目的としています。
そもそもの前提知識がないと、
解説を見ても「何のこと?」と
ハテナがいっぱいになるわけです。
会計上と税法上って何が違うの?
会計上ってそもそも何?
税法って何?
財務諸表って何?
法人税の申告書って何?
こんな感じで、解説から派生して、
そもそもの言葉の意味を知るところから
始まるんですね。
イメージとしては、
原点➡前提知識1➡前提知識2➡前提知識3
➡問題➡解説
となっているので、解説だけみても、
それ以前の前提知識が入っていないと、
何のことを言っているのか
さっぱり分からないと沼にハマるわけです。
そこで、そもそもこれって何?と調べて、
調べたことから更に、調べていくと、
原点に辿り着くわけです。
解説から、逆算して調べていくことで、
原点の知識を得ることができます。
解説➡問題➡前提知識➡前提知識・・・
という流れで1つずつ巻き戻していくので、
私は巻き戻し勉強法と呼んでいます。
慣れるまでは時間がかかるのですが、
1度理解してしまえば、
FP2級の問題が面白いぐらい
スラスラ解けるようになります。
枝葉の知識ではなく、
幹の土台を固めるわけなので
全体像がしっかり見えるようになります。
多少言い回しが変わったとしても
本質が理解できていれば、
正解か不正解か分かるわけです。
なんなら問題作成者の意図まで見えてきます。
「あぁ、受験生にここで引っ掛けさせたいんだな」と、魂胆まで見抜けるようになるのです。
焦りは禁物
試験日が刻一刻と近づいてくると、
気持ちが焦り、早く他の分野も勉強しないと・・・
となりがちです。
そうなると、解説を読んでも
いまいち分かっていないけれど、
なんとなく雰囲気で覚えておこうとなります。
とりあえず表面上だけをなぞって、
次の問題に進むことが増えます。
でも、それだとちゃんと理解している
わけではないので、
数日経てばまた同じ問題で間違えます。
そして点数がなかなか伸びず、
焦る気持ちだけがどんどん大きくなるんです。
試験本番で合格するためには
満点を取る必要はありません。
それよりも
頻出問題や基礎問題を
いかに落とさないかが重要です。
巻き戻し勉強法が習慣づいていると、
定番の問題が出たときに確実に得点源に
することができます。
その1点の積み重ねが合格に近付きます。
今、FP2級の勉強に苦戦している方は、
ぜひこの巻き戻し勉強法を使って
「そもそもそれって何?」と常に問いかけながら
「分かる」を増やし、
「解ける」に変えていってください。
応援しています!